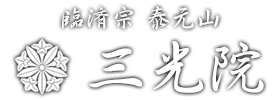尼門跡寺院とは
尼門跡(あまもんぜき)寺院とは、皇女や王女、あるいは公家や将軍家の息女が入寺した寺院を指し、そこでは皇室ゆかりの御所文化が育まれ、独特な宗教儀礼と信仰生活が形成されました。
「尼門跡」あるいは「門跡尼寺」と公称するようになったのは、昭和16年(1941)からで、中・近世には「比丘尼(びくに)御所」や「尼御所」と呼ばれました。通常の尼寺とは一線を画しています。
修行や仏教儀式はもちろん、文学や芸術にも親しみ、住まいも一部が御所から移築されたり、調度や道具類、室内の装飾にいたるまで王朝風の生活が営まれていました。
明治維新以降、神仏分離令によって、皇女の出家が禁止されてから、尼門跡の文化を伝える寺院の数は減っていき、今残っているのは、京都7寺(大聖寺、宝鏡寺、曇華院、光照院、林丘寺、霊鑑寺、三時知恩寺)と奈良3寺(円照寺、中宮寺、法華寺)。